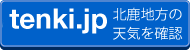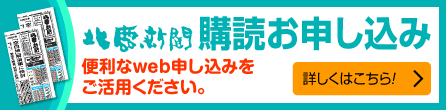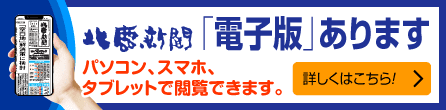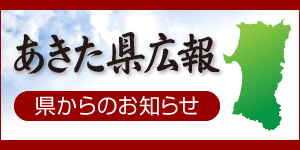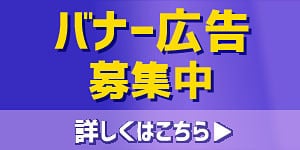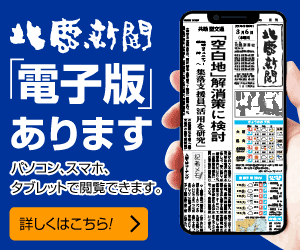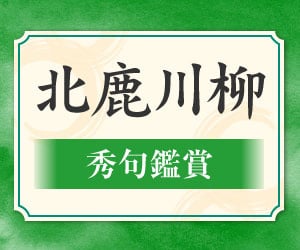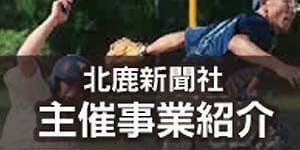今日のニュース
2024年4月
結婚支援関連事業 若年層中心に利用広がる 大館市 住宅購入や賃貸費補助
2024-04-25
NEW
大館市は、市民を対象とした結婚支援関連4事業を本年度も継続する。新婚世帯の住宅購入費などを補助する「結婚新生活スタートアップ支援」は、補助上限を引き上げた若年世代を中心に利用が広がり、昨年度実績は過去最多の31件だった。ほか2事業も累計でそれぞれ200件を超えた。結婚の希望をかなえ婚姻費用の負担を軽減するとともに、人口減少の抑制を図り定住促進を目指す。
国境超えて絆深める 台湾の修学旅行生 国際中と下川沿中を訪問 伝統芸能など体験
2024-04-25
NEW
北秋田市阿仁打当の阿仁熊牧場「くまくま園」で24日、今年生まれたツキノワグマ3頭が報道関係者にお披露目された。いずれも雄でこのうち2頭が双子。今季営業開始の27日から一般公開される予定で、園関係者は「ゴールデンウイーク(GW)頃までは、赤ちゃんらしいかわいい姿を見ることができる」と話している。
琴の演奏体験を通じて交流を深める台湾の生徒と国際情報中の生徒(同校)
川口獅子踊りの太鼓演奏について教える下川沿中の生徒(同校)
子グマ3頭が仲間入り 北秋田市 くまくま園 27日から一般公開
2024-04-25
NEW
鹿角市 市民対象に購入補助 エアコン 冷蔵庫 省エネ家電に最大20万円
2024-04-24
鹿角市は本年度の新規事業として、省エネルギー型の家電製品(エアコン、冷蔵庫)を購入する市民に対し、費用の一部を助成する。家庭から出る温室効果ガスの排出抑制と光熱費の削減を図る目的。補助率は2分の1。1製品につき上限10万円、エアコン、冷蔵庫の両方を購入する場合は最大20万円の補助となる。受付期間は5月1~13日。応募者多数の場合は同15日に抽選を行い、申請できる100人を決める。
桂城小と城南小 〝誕生日〟祝い記念集会 大館市 同じ母体、共に歩み
2024-04-24
「社長とお話しませんか」―。秋田内陸縦貫鉄道(本社・北秋田市、吉田裕幸社長)が内陸線阿仁合駅で始めた「社長呼び出しシステム」が好評だ。利用者と吉田社長が駅で直接対面し、内陸線に関する質問から旅の話などまで気軽にできるシステム。吉田社長は「これまで以上に内陸線を身近に感じてもらえたら」と話している。
メッセージを貼り付けたバースデーケーキも登場し、誕生日を祝った(城南小)
「桂城城下町かるた」の絵札を取り合う児童(桂城小)
2024年3月
コロナワクチン接種 関連事業3年で10億円 大館市 ドームで1日最大9千人
2024-03-30
大館市は今月末で、新型コロナワクチン接種対策室を廃止する。感染症法上の位置付けが5類に引き下げられ、これまで進めてきた事業にめどが付いた。ニプロハチ公ドームで1日当たり最大9200人に対応するなど、2021年2月から累計で30万3120回(月末の予約含む)を実施。接種に関する事業費は3年間で総額10億8900万円に上った。
今冬の降雪量 19年度と並び過去最少 記録的な暖冬 大館市で累計199㌢
2024-03-30
全国的に記録的な暖かさとなった今冬は各地で雪が少なく、北鹿地方でも顕著な「少雪」となった。大館市消防本部によると、同市の2023年度の累計降雪量(23年11月~24年3月)は199㌢にとどまり、観測を始めた08年以降で最も少なかった19年度と並んだ。同市の除雪ボランティア「ハチ公スノーレンジャー」の利用申請も初のゼロ。冬らしからぬ時節となった。
豊作願い種駒打つ 大館市山田 「キノコの里」へ栽培開始
2024-03-30
鹿角市 人口構造の若返りなど 24、25年度 7次総実施計画を策定
2024-03-30
鹿角市は、第7次総合計画・前期基本計画の実施計画を策定した。計画期間は2024年度から2年間。最重要課題である「地域の稼ぐ力を高める産業の振興」や「人口構造の若返り」「30年カーボンニュートラルの目標実現」などに向け、279事業の概要を掲載している。
経営課題を伴走型支援 大館商議所 議員総会 新年度予算を承認
2024-03-30
新年度の事業計画を承認した議員総会(プラザ杉の子)
大館商工会議所(佐藤義晃会頭)の通常議員総会が29日、大館市のプラザ杉の子で開かれ、2024年度事業計画と予算の議案2件を原案通り承認した。人手不足など中小企業を取り巻く経営環境が大きく変化する中「伴走型個社支援」に引き続き注力する。